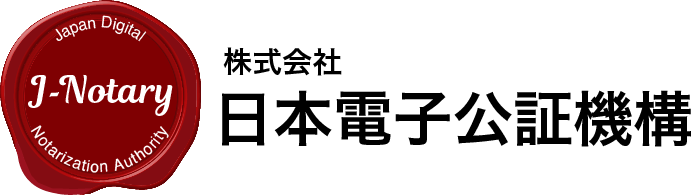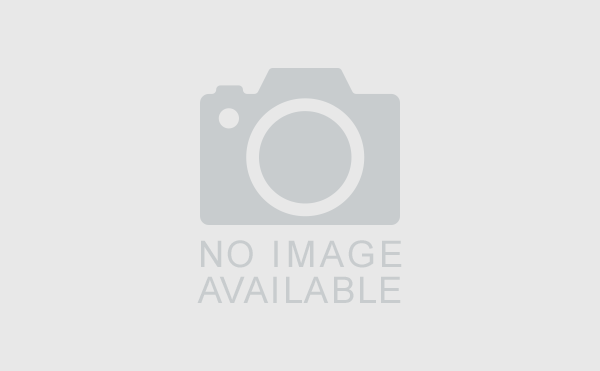第114回コラム 「海底資源の採掘技術について調査してみました」
今回は、東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」から徒歩約7分に鎮座する椙森神社(スギノモリジンジャ)(中央区日本橋堀留町1丁目10-2)をご紹介します。同神社は、社伝によれば平安時代に平将門の乱を鎮定するために、藤原秀郷が戦勝祈願をした所といわれています。




(筆者撮影)
リチウム電池や強力マグネット等には無くてはならないレアアースは、戦略物質としの位置づけが高まっています。例えば、中国は世界のレアアース精製の約90%を担い、EV・風力・軍事などの重要産業を支えています。
中国は、輸出規制を通じて米国や日本に対する交渉力を高め、戦略的資源として位置づけています。
我が国は、排他的経済水域(EEZ)に存する海底資源に着目し、深海から鉱物資源を回収する技術の開発に官民挙げて取り組んでいます。
そこで、海底資源の活用に必要な採掘技術に関する特許・実用新案情報を調べてみました。
1.出願年別出願件数
FIがE21C50が付与された特許・実用新案の公開公報を調査したところ、474件ヒットしました。
グラフ1に示すように、出願件数は1970年代と2010年半ばから2020年代半ばまでの二つの山が現れました。
【グラフ1】

1970年代は、マンガン団塊や海底熱水鉱床の存在が確認され、実海域での採鉱実験が可能になったためであると思われます。
2010年半ばから2020年代半ばまでは、ドローン技術の進歩や電気自動車の普及促進に伴うレアメタル・レアアースへの需要増加が考えられます。
2.FI(技術分野)別出願件数
FIによる分類では、下記の分類になります。
第1位は、E21C50/00他に分類されない水中からの鉱物の採取
第2位は、E21C45/00水力採鉱法
第3位は、E21C50/02船の運動にたよるもの
第1~3位で全体の64%を占めていますので、これらの技術が実用化のポイントになると思われます。
【グラフ2】

E21C50/00:他に分類されない水中からの鉱物の採取(サクション浚渫機またはその構成部品E02F3/88;掘削物の移送または分離のための装置E02F7/00;水中井戸から石油,ガス,水,溶解性または溶融性物質を採取するために特に適合した方法または装置
E21C45/00:水力採鉱法;水力モニタ
E21C50/02:船の運動にたよるもの
3.筆頭出願人別の出願件数
グラフ3は、筆頭出願人別の出願件数です。
三菱重工㈱が他を10件以上引き離して断トツ一位です。
ハイドレード※1採掘に強みを持つようです。
第2位の三井造船㈱も、ハイドレード採掘に強みを持つようです。
第3位の日本鋼管㈱は、1990年の出願が最後であり、現在は撤退したものと推測されます。
同数第3位の古河機械金属㈱は、当初東京大学、その後、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構と共同して開発し、水流揚鉱方法に強みを持つようです。
※1:メタンやエタン、二酸化炭素などのガスと水によって作り出された氷状の物質
【グラフ3】

我が国は、天然資源が少ないことから、海底資源の採掘技術を世界に先駆けて実用化することが強く望まれます。
次回は、技術内容に関し、解説したいと思います。 以上